ペース配分
管理人は資格試験の受験勉強では、1つの問題集を3回以上繰り返すことにしています。
管理人が乙種 危険物取扱者試験 第3類を受験した時の1カ月のペース配分は、おおよそ次の通りでした。 乙種を受験する方の参考になると思います。
(1回目) 約3週間
(2回目) 約3日
(3回目) 約2日
(4回目以降) 試験日まで数日
管理には以前公害防止管理者試験を受験したことがあります。 公害防止管理者試験の受験勉強期間は2カ月でした。
今回の危険物取扱者試験では受験勉強期間がたった1カ月しかありませんでした。 ところが・・・ 結果的には試験日の数日前には受験勉強が終わって、やることがなくなってしまいました。 もちろん、甲種を受験する方は1カ月では足りないと思います。
では、いよいよ具体的な勉強法を紹介します。
黄色蛍光ペンでマーク
問題集の暗記すべき文章に黄色蛍光ペンでマークします。 ちなみに、色ボールペンは線の曲りが気になったり、目立たなかったりするのでよくないです。 また黄色以外の蛍光ペンは裏のページに透けてしまうのでよくないです。 結局、黄色蛍光ペンが最も良いです。
(注意) 分からないことをすべてマークすると大変時間がかかります。 問題集が黄色のマークだらけになると覚えるのに時間もかかります。 問題集の1回目の受験勉強では、問題で分からなかったことに黄色蛍光ペンでマークし、出題されていないことを欲張りすぎてマークし過ぎない方がよいです。 一覧表なんかがあると全部覚えなければ、と思うのですが、実際には出題されるのは特定の部分だけということもあるので。
ちなみに、消える蛍光ペン(フリクションライト)があります。 便利ですね。
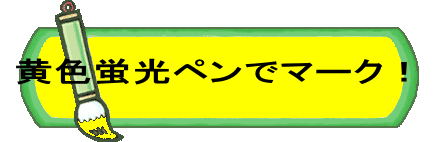
前日の復習をしてから、その日の勉強開始
昨日の続きを勉強する前に、昨日勉強した部分を復習します。 黄色蛍光ペンでマークした部分だけでよいです。 管理人はこの方法を実行してから、問題集の2回目の勉強がかなり楽になりました。
ちなみに、この方法はエビングハウスの忘却曲線を根拠にしています。 興味のある方のため、リンクを貼りました。
公害防止管理者試験に合格しよう!-エビングハウスの忘却曲線まず問題を解く。 次に説明を読む。
管理人は、鈴木幸男著「鈴木先生のパーフェクト講義乙4類危険物試験」で勉強しました。 この問題集は説明、問題の順に記載されています。
問題集の前のページから、説明を暗記し、問題を解くのですが、解けない問題が多いことに気づきました。 そこで、まず問題を解き、問題の解説を読んだ後に、説明の関係する部分を暗記するようにしたところ、解けない問題が減りました。
簡単な問題はスキップ
管理人は理系です。 危険物取扱者試験の「基礎的な物理学・基礎的な化学」の内容は法令よりも簡単でした。 簡単に解ける問題を何度も解くのは時間の無駄なので、簡単な問題の問題番号には×を記入し、二度と解かないことにしました。 もちろん、「危険物に関する法令」でも簡単な問題はスキップしました。